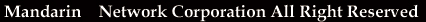税金について学ぼう「相続税」 その二
こんにちは。
スーパー台風がようやく日本列島から去りましたが、各地で大きな被害が出ているようです。
土砂災害など、これから発生するものありますので、どうぞお気を付けください。
本日は、前回の続き、相続税についてです。
来年度からの増税を見越して、早くも動き始めている方もいるようです。
今回は増税の背景などについて勉強しましょう。
相続税は、経済成長やインフレで相続財産が増えて税負担が重くなることへの配慮から、段階的に減税されてきました。
この流れが、バブル崩壊で地価が下落した後も続き、死亡者数に対する課税件数の比率は2012年に約4%と、
1987年の約8%から半減しました。
今回は相続税増税には、「富の再配分」機能を高める狙いがあります。
増税のポイントは、課税対象額を減らせる基礎控除を4割縮小することです。
法定相続人が3人の場合、基礎控除は8000万円(5000万円+1000万円×3人)から、
4800万円(3000万円+600万円×3人)に減ります。
遺産総額7000万円だと、現在は基礎控除より少なく相続税はかかりませんが、増税後はかかる公算が大きいです。
最高税率も、50%から55%に引き上げられます。
同居の親族が相続するなどの条件を満たせば土地の評価額を8割減らせる特例は、
現在240平方メートルまでしか認められませんが、来年1月からは330平方メートルに拡大されます。
これは減税効果がありますが、基礎控除縮小の影響が大きく、全体では増税となります。
財務省によると、増税によって課税比率は約4%から約6%に高まり、
相続税収(年1.5兆円程度)は約2200億円上積みされます。
地価が高い東京23区に限れば、比率は2割に達するとの見方もあります。