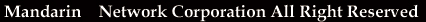相続税増税
こんにちは。
朝晩だいぶ冷えてきましたね、風邪が流行る季節です、お気を付けください。
先日、ブログでご紹介した「相続税の基礎」が非常に好評で、反響も多くたくさんの質問を受けました。
本日は、その中から一つ、不動産に関係のあるご質問を題材に、
皆さんとの情報共有という意味も含めてQ&A方式でお話ししていきたいと思います。
Q.「来年からの相続税増税で、課税対象者が増えると聞きました。相続財産が自宅だけでも相続税がかかるのですか?」
A.来年から実施される相続税改正は、
(1)基礎控除の引き下げ
(2)最高税率の引き上げ
(3)未成年者などの控除額の引き上げ
(4)小規模宅地等の特例の限度面積拡大
の4点が柱になっています。
就中、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。
現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、
相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。
これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、
来年からは6%程度に増えるといわれています。
ご質問のように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高くなります。
ですから、事前の対策が重要となります。
たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。
しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。
二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。
とはいえ、それが難しい場合が殆どではないでしょうか。
残る手段は、税理士とお話しをされ、しっかりと納税資金を準備しておくことです。
少子高齢化時代におけ税収確保、今後も様々な税金の増税が考えられます。
このスペースで、勉強していきましょう!