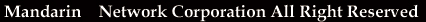税金について学ぼう「相続税」 その三
今日は一気にいきましょう!
では、その対策方法などはどうしたらよういのでしょうか?
相続税対策として、課税対象額を減らして納税額を抑える方法はいくつかあります。
いずれもデメリットがあり、慎重に検討したいです。
対策の定番と言えるのが、預貯金や土地などを子や孫に譲る「生前贈与」です。
1人あたり年110万円までは贈与税がかからないため、譲る相手が3人いれば、
無税で年330万円ずつ減らすことができます。
ただ、毎年決まった額を贈与すると、「計画的な税逃れ」とみなされ贈与税がかかる場合があります。
死亡から遡って3年以内に贈与した資産は、相続財産に組み込まれます。
過度の贈与で自らの預貯金が不足する事態も避けたいです。
贈与には特例もあり、子や孫の教育費は1500万円、住宅資金は最大1000万円まで非課税。
高齢者の資産を若い世代に移す狙いで、それぞれ来年末、今年末が期限となっています。
非課税財産を増やす手もまります。
死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで課税されません。
墓や仏壇、仏具、神棚なども非課税で、相続税増税が決まった昨年以降、
金製の高価な「おりん」や仏像を買い求める人が増えているといいます。
これらは、日常的にお参りしていないと、投資目的とみなされて課税される可能性があります。
不動産を所有する人には、賃貸住宅経営も選択肢となります。
賃貸に回せば、土地や建物の評価額を最大30%減らせるからです。
しかし、入居者が集まらなければ十分な賃料収入が得られず、評価減の特例も享受できません。
ローンの負担ばかりが重くなる恐れもありますので気をつけてください。
それでは、海外の相続税はどうなっているのかも、参考までに見てみましょう。
相続税は米国や英独仏など欧州主要国にもあります。
英米は遺産額に応じて税額が変わり、独仏は遺産額と相続人の数に応じて変わります。
日本の制度は独仏に近いようです。
多くに国は、配偶者の相続には非課税枠を設けるなど一定の配慮をしています。
ただ、米国は、富裕層の支持が多い共和党のブッシュ政権での決定を受けて2010年に廃止し、
民主党のオバマ政権が11年に復活させた経緯があります。
他にも、相続税がかからなかったり、相続税を廃止したりした国は少なくないです。
経済協力開発機構(OECD)に加盟する34か国のうち、
相続税がない国は10か国(オーストラリア、オーストリア、カナダ、エストニア、イスラエル、、メキシコ、ニュージーランド、
ポルトガル、スロバキア、スウェーデン)あります。
シンガポールやスイスは相続税がない上、所得税の水準も低いため、
近年は日本の富裕層が生活の拠点や資産を移す「租税回避」の動きが広がっています。
世界各国に比べ、平均して日本の税率は高いというイメージがありますよね。
相続税に関しても、どうやらそのようです。
お持ちの不動産の税金についての勉強をするよい機会かもしれません、
今後も、法改正時に限らず、様々な情報を皆さまに届けていきたいと思います。